降圧剤不要

80代♂
10数年健康管理として
週に一度の鍼灸治療で通院されている御夫婦
お二人とも持病があったが現在は極めて良好
御主人は最近20年以上内服していた降圧剤がいらなくなった
主治医から「長年降圧剤を内服している80代の患者さんが、
内服を中止した例は極めてまれ」と驚かれていたそうだ
血液検査の経過も極めて良好で
医師から99点とお誉めの言葉を頂いたと大層喜ばれた
我々の臨床では珍しくはなく
降圧剤の減薬・中止した症例は多数経験している

80代♂
10数年健康管理として
週に一度の鍼灸治療で通院されている御夫婦
お二人とも持病があったが現在は極めて良好
御主人は最近20年以上内服していた降圧剤がいらなくなった
主治医から「長年降圧剤を内服している80代の患者さんが、
内服を中止した例は極めてまれ」と驚かれていたそうだ
血液検査の経過も極めて良好で
医師から99点とお誉めの言葉を頂いたと大層喜ばれた
我々の臨床では珍しくはなく
降圧剤の減薬・中止した症例は多数経験している

60代♀
2日前に突然背部の激痛で動けなくなり
救急外来受診、内科新患を疑い全身の精査の結果異常認めず
原因不明としてロキソ二ン処方される
激痛は軽減傾向ではあるが、強い背部痛と、寝返りが困難な頚部痛
体表観察で脊柱の大きな側弯が認められたので
左章門に蓮風鍼置鍼10分
抜鍼後には大きなS字状の側弯と背部痛は消失
空間診で章門は帯脈穴とともに身体の歪を整える重要な穴処
顕著な左右差が認められる場合は奏功する

母校の鍼灸学校から卒業年度の在学生の治療院見学の依頼があった
お世話になった母校でもあり進んで申し入れを受けた
鍼灸臨床を公開することは
鍼灸師を目指す学生にとっては
貴重な体験でもあるし
我々スタッフにとっても
院内に学生がいることによって良い緊張感も生まれる
叉、臨床のイロハを教えることは
教育という意味でまた臨床とは違う刺激が得られるのだ
この見学を受け入れる鍼灸治療院が少ないのが、実はこの業界の大きな問題
一人で患者さんを見ているから他人が入られるのを嫌う鍼灸師が多い
治療方針や理論に自信がなく受け入れない
学生に見せるほど患者さんがいない
等々、様々な理由があるようである

東洋医学の重要な診察法のひとつに「望診」がある
「望診」とは患者さんの表情、姿勢、動き方、顔の気色、肌肉の状態、etc・・・
ありとあらゆる視覚から入ってくる情報を得ることをいう
ココロのありようも見て取れるようになると一人前
長年臨床をしていると、何気なく直感的に人を診る習慣がついているので
患者さんだけでなくスタッフへや家族、友人にも無意識で望診をしている
臨床家は「直感力」がとても大切
「病を見分ける直観力」を養うには長い時間がかかるが
個人差もあり1~2年で優れた能力を発揮することもある
休日でも人がいれば常に人間観察をすることだ
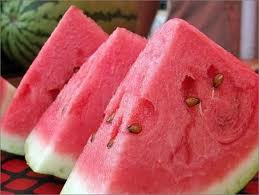
明日は二四節気では大暑
暑さが最も厳しくなるというが
偏西風の蛇行で低温が二日続き
先日の猛暑からの急変に身体がもたず
所謂夏バテを訴える患者さんが多い
脾虚の素体がある人は飲食不節に注意
休養や睡眠を十分とり
規則正しい生活を心がけたい

ROTO Therapyによる頚部ジストニアの症例
30代♀
数年前からの頚部ジストニアによる不随意の頚部左回旋運動
右上肢外旋系(SUPINO)障害Testで陽性
左三陰交切皮置鍼しつつ、頸部左右の自動運動を数回
治療後に正面を向けるようになる
明らかに有効で客観的にも付随運動がの消失を確認できた
経過観察が必要であるが
難治性の頚部ジストニアに光明が見えてきた

目の下のクマは女性には気になる存在
睡眠不足や、ストレス等が重なり
お血を形成すると現われる
三陰交や足臨泣などで駆お血の治療をしながら
最も著効なのは風池の刺絡
とても良く効くので患者さんからリクエストがある
勿論希望されてもその日の状態によって
風池の刺絡をするとは限らないが
確かに客観的にクマの軽減が認められる
大切なのはお血の予防で
適度な運動やバランスのとれた食生活が大切
http://www,.n-acp.com

7月16日(月)に名古屋駅のWINC AICHにて
公益社団法人日本鍼灸師会主催
「第3回臨床鍼灸スポーツフォーラム」が開催され
私の友人でありスポーツ障害のプロフェショナル
山梨県の溝口哲哉先生が「ダイナミック鍼灸!!スポーツ障害とROTO Therapy」
の演題を引っ提げて名古屋に乗り込んできます
今迄の鍼灸理論を覆すよな「動きと鍼灸」についての
全く新しい理論と実技を披露していただけるので
おおいに楽しみにしている
http://www.harikyu.or.jp/pdf/sports_forum3rd_120526.pdf

今夜は院内勉強会
在宅往診中の患者さんのカンファレンスを11件
日頃往診スタッフに任せっきりの見えない患者の状況報告を受けた
後半は金と銀の古代鍼の違いを実技を交えて皆で体感した
ブラインドテストで
金の古代鍼は翳すだけで暖かくなり
銀の古代鍼は翳すだけで冷えを感じる
温補法と清熱瀉法が自由自在に操れることを実感し
その鮮やかな変化に皆が驚き
臨床への生かし方を再検討した
http://www.n-acp,com

SD(痙攣性発声障害)や機能性発声障害で
多くは百会(督脈)を使うと経過がよい
陽気が昇る病症で反応がよく出る経穴なので
上手く使うと気を下に引き降ろす作用が働き
発声しやすくなる
梅核気のように喉の周辺の気滞にも良く効く
適応を見極める感覚と経験が必要な経穴だ
http:www.n-acp.com
〒468-0023
名古屋市天白区御前場町(ごぜんばちょう)13番地
(052)804-8190
月:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00
火:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30
水:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30
木:休み
金:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00
土:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00
日:休み
祝日:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00
該当する方を選択してください
